“誰ひとりやらされている人がいない” 楽しみながら地域とつながる実践力
美作大学調理師会
助成を受けた団体が助成金をどのように活用してきたのか、またその活動が地域にどのような影響を与えているのかを取材しました。津山市にある美作(みまさか)大学の「美作大学調理師会」の学外顧問(助成当時は部長)・牧原直太朗(まきはら なおたろう)さんにお話を伺いました。(取材・文/大島 爽)
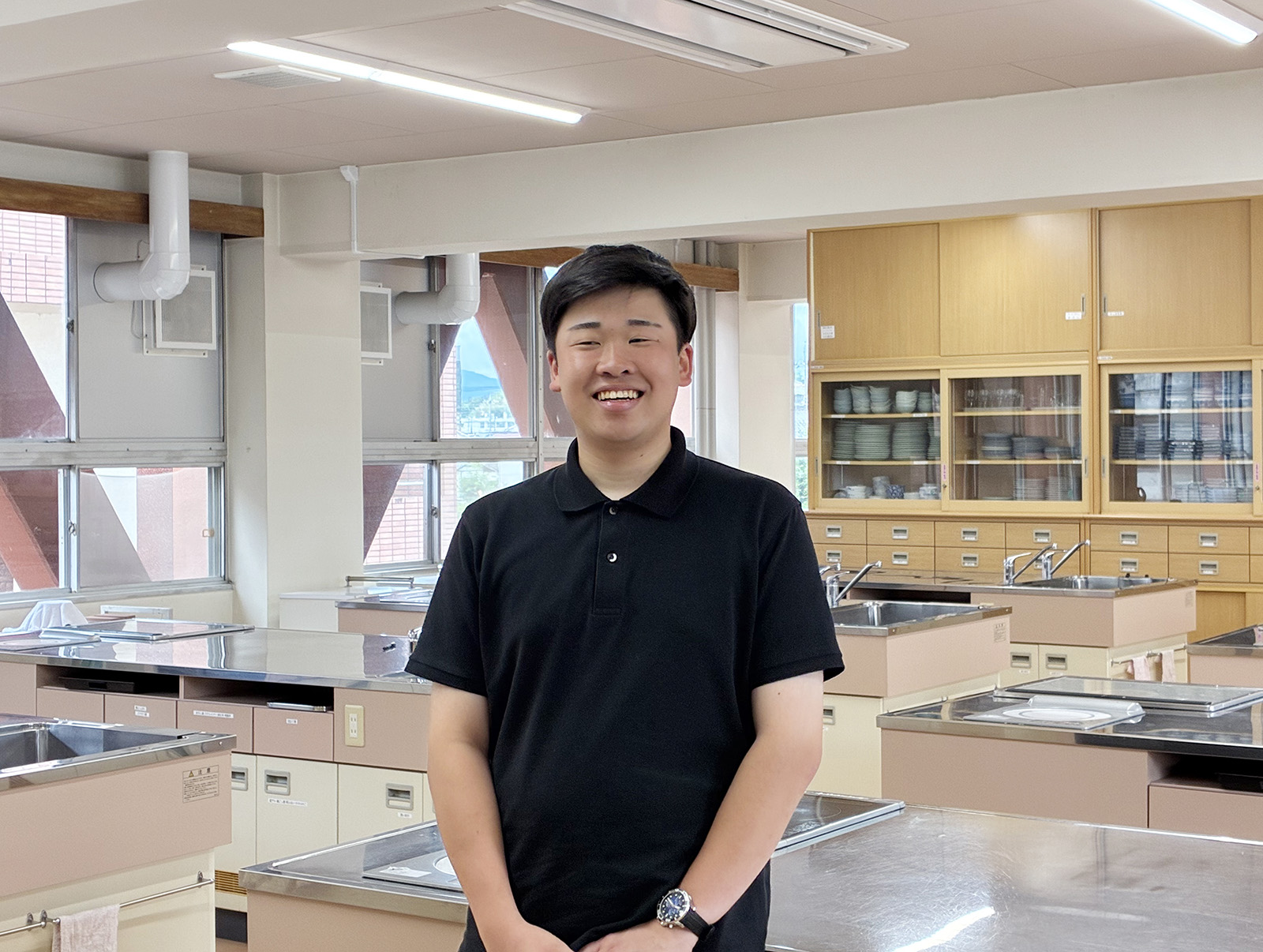
美作大学
美作大学は、岡山県津山市にある学校法人美作学園が運営する私立大学です。その歴史は1915年に創立された津山高等裁縫学校にさかのぼり、その後、女子大学の開学、共学化などを経て、現在は「美作大学」と「美作大学短期大学部(※2025年度以降募集停止)」の2つの高等教育機関を擁しています。
大学には食物学科、児童学科、社会福祉学科の3つの学科があり、生活科学を軸とした専門的な教育を展開しています。学生は沖縄・高知などの県外出身者も多く、地域との連携や実践的な学びを重視したカリキュラムが特色です。
美作大学調理師会
美作大学調理師会は、食物学科(管理栄養士養成課程)に在籍する学生を中心に構成された、美作大学公認のクラブ活動※です。
※美作大学の課外活動は、「サークル(予算に上限あり)」と「クラブ(実績に応じて予算が変動)」に分類されています。美作大学調理師会が当財団の助成を受けたのは、サークルとして活動していた時期のことです。
2021年に調理師免許を持つ学生2人が立ち上げ、すぐに参加した「美作国“美味し国”プロジェクト」では、地域食材を活用したメニュー開発に取り組み、同チームのレシピが「開発グルメ“美味し食”」として2022年3月に認定されました。さらに同年11月には、「第5回ご当地タニタごはんコンテスト」で考案したメニューがグランプリに選ばれるなど、全国的にも注目を集めました。メンバーは立ち上げ当初の2人から20人以上に増え、より本格的なサークル活動へと発展していきます。
その後も意欲的に活動を続け、2023年4月には美作学園が運営していた施設「みまっぱぷらざ」にて「月一(つきいち)ランチ※」と称し、地元食材を使ったメニューを、地域住民に提供する取り組みを始めました。また、メニューの原材料に「つやま和牛」を取り入れ、津山市の特産品PRにも一役買ったり、地元の企業やイベントとのコラボレーションでメニュー開発したりなど、地域に根ざした実践的な活動を広げます。
※「みぱっぱぷらざ」では4回開催。同施設は2023年12月に閉店したため、2025年7月現在は「みぱっぱぷらざ」での月一ランチは開催していません。


数々の実績と学生たちの熱意ある活動が大学に認められ、2024年度にはサークルからクラブへと昇格。学内外から、より注目や期待が寄せられる存在となりました。2025年3月にチームを立ち上げたメンバーは卒業しましたが、その志は受け継がれ、現在も後輩たちが意欲的に活動を続けています。
美作大学調理師会(クラブ・サークル)
「美作国“美味し国”プロジェクト」で、食物学科1年生考案のレシピが認定される(学科トピックス)
美作国“美味し国”プロジェクト
ご当地タニタごはんコンテスト
授業から生まれた小さなチームが、地域に根差したサークルへ

―牧原さんが美作大学調理師会を立ち上げたきっかけはなんですか?
牧原:大学2年生時の授業の一環で、美作県民局主催のレシピ開発事業「美作国“美味し国”プロジェクト」に出ることになったのがきっかけでした。プロの料理人や飲食店のシェフのほか、高校生や大学生も参加する形式で、美作大学からも何チームか出ることになったんです。そのとき、出場チーム名が必要となり、僕ともう1人、調理師免許を持っている学生2人でチームを組んでいたので、「美作大学調理師会」として活動しました。最終的にそのコンテストでは、僕たちのチームだけが残って、レシピ認定されることになりました。授業内での活動としてスタートした小さなチームが、やがてサークルとして動き出した、という流れです。
―美作大学調理師会のコンセプトはありますか?
牧原:活動の方針は、「メニュー開発をしてみよう」とか「地域の活性化イベントに参加してみよう」というのと同時に、「いろいろなコンテストに積極的にチャレンジして、成果を出していこう」というものです。試作にかかる費用はサークル側で負担するようにして、「やってみたい!」って思った人が挑戦しやすい環境をつくりたいと思いました。正式にサークルとなって出場した「第5回ご当地タニタごはんコンテスト」ではグランプリを受賞しました。
―立ち上げて早々に、レシピ認定やコンテストで受賞など、順風満帆ぶりが伺えますが、これまでの活動の中で、大変だったことはありませんでしたか?
牧原:大変なこともちょこちょことあったとは思うんですけど、確かに順風満帆だったのかもしれません。というのも、大学のサポート体制がしっかりしていたからです。食物学科の充実した調理設備はもちろん、料理や衛生に関する専門家の先生方が揃っているので、壁にぶつかってもすぐに相談できる環境がありました。
ただ、チームの人数が増えていく中で、せっかく頑張ろうとしてくれるメンバーがいるのに、僕が全体的にうまく仕事を回せなくなって、いっぱいいっぱいになった時期はありました。そんな中でも自分なりに試行錯誤していたら、だんだんとメンバーの方から「これ、やっとくよ」と自然に動いてくれるようになりました。経験を積み重ねながら、少しずつ人を率いる力みたいなものが身についていったかもしれません。

ー順調にメンバーが増えていった理由はなんだと思われますか?
牧原:理由はいくつかあると思います。まず、広報室で顧問をしてくださっていた方が、活動を記事にして発信し、サポートしてくださっていたこと。
それに加えて「月一ランチ」をはじめとする、地域に出る「見える活動」が多く、注目を集めやすかったんだと思います。自分たちが好きなことをやっていたのですが、結果的に地域貢献的な要素が強くて、それに魅力を感じてくれる人が多かったのかもしれません。美作大学の入試の際に、高校生から「美作大学調理師会に入りたいんです」という話もあったそうです。
あと、僕自身はもちろん、メンバーのみんなも本当に楽しんでいるんですよね。クラブの顧問からも「誰ひとり、やらされている感じの子がいない」とよく言われていました。そんな雰囲気も伝わっていたんだと思います。
助成金のおかげで一気に活動の幅が広がり、実績を積み重ねることができた
―牧原さんは美作大学に入る前、津山東高等学校の食物調理科在学中に活動していた「東雲(しののめ)キッチン」でも、当財団の助成を受けられたと聞きました。「東雲キッチン」とは具体的にどのような活動だったのでしょうか。
牧原:僕が高校2年生のときに、真庭市で「消防士の台所」という、消防士さんが賄い料理を作って提供するイベントがありました。地域活性化が目的の団体に関わっていた叔父から、その話を聞く中で、「調理科の高校生でもできるんじゃない?」と思いつき、高校の先生に相談して一緒に考えた企画です。
「東雲キッチン」は、固定のお店ではなくイベントの名前で、間借りでお店をやったり、イベントに出店したり、移動しながら活動するスタイルです。部活ではない「調理研究同好会」という有志のグループで活動し、その代表を務めていました。同じメンバーで、2019年に新潟で開催された全国高校生クッキングコンテストにも出場し、金賞(文部科学大臣賞)を受賞しました。
ぼくが、わたしが活動を始めた理由「地域食材を使った高校生によるシノノメキッチンの開催」
注目!今月の津山(広報津山2020年1月号)

―当財団からの助成を受けられることを、高校生だった当時どのように知ったのでしょうか。
牧原:2019年に「ジブンゴト学会」という、高校生がやりたいことをプレゼンするイベントが岡山大学でありました。そこで僕たちの発表を聞いてくれた、主催者の「備中志事人」の方が声をかけてくださって、「こんなのもあるよ」と、福武教育文化振興財団さんの助成について教えてくれました。
僕たちだけではどう申請したらいいのか分からなかったのですが、高校の先生方に全面的に協力いただいて、2020年に助成を受けることができました。
―その後、美作大学調理師会としては2023年に助成を受けられましたが、助成によって良い変化はありましたか?
牧原:助成をしていただいたおかげで一気に活動の幅が広がりました。大学の学友会から出るサークルの予算は上限が2万円なんですけど、ちょっと食材を買ったり備品を揃えたりすると、すぐに使い切ってしまいます。試作費すら出せないような状況だと、やっぱり継続的な活動をするのが厳しいんですよね。その代わり、外部の団体から助成を受けることはOKだったので、高校生の時にもお世話になった福武教育文化振興財団さんに申請させていただくことにしました。
―具体的には、どのようなことに助成金を活用されましたか?
牧原:2023年の「月一ランチ」という企画では、考案メニューの試作費に助成金を充てさせてもらいました。それまでは、3人くらいで実費を出し合って「これは高いから、こっちの安いので我慢しようか」となることもあり、本当に使いたい食材じゃなくて、妥協したもので試作して、不完全燃焼に終わってしまうこともありました。でも、助成金のおかげで納得いくまで試作ができ、やりたかったことにちゃんと取り組めたなと思います。
あとは消耗品ですね。キッチンペーパーとかアルコールタオル、手袋等の衛生用品。販売するとなると食中毒とか本当に気をつけないといけないので、そういうところで余裕を持って準備できたのはすごくありがたかったです。
ほかにも屋外イベントだとテントが必要だったり、テーブルとかも必要です。足元が土の場所ならブルーシートを敷かないと埃が舞ったりもするし。活動をするために必要な細かい備品には案外お金がかかるんです。そこを気にせず、料理を考えることに集中できたのは大きかったですね。
―助成を受けたことで、活動に集中できたということですね。
牧原:予算を気にし過ぎなくても良くなり、心に余裕ができました。福武教育文化振興財団さんからは上限30万円の助成をいただいたのですが、それまで大学から出る予算が2万円だったので、金額のギャップに「何に使おう?」と戸惑うほどでした。
―現在は助成を受けていませんが、運営や活動費はどのように調達されているのでしょうか?
牧原:助成をいただいた2023年は、毎月さまざまなイベントに取り組めたので、実績報告書も、A4で30枚以上になるほどでした。それらの成果が評価されて、2024年度にはサークルからクラブへの昇格が認められ、大学から助成金と同等以上の予算をいただけるようになったんです。それにより、外部の助成がなくても活動を継続できる体制が整いました。
本来、クラブに昇格するのはすごく大変で、時間がかかるものなんですけど、美作大学調理師会は設立からたった2年で昇格して、「前代未聞のスピードだ」と言われました(笑)

―牧原さんは2025年3月に大学を卒業し、現在は学外顧問という肩書きですが、美作大学調理師会とはどのように関わっていかれるのでしょうか。
牧原:大学には本来の顧問の先生がいらっしゃるので、僕が直接的に今すぐ何かをすることはないですが、「コンテストがあれば手伝うよ」とか「イベントに出店するなら道具を運ぶよ(笑)」と言っています。呼んでもらったら、なんでも応えるスタンスです。
現在、食品関連の一般企業で働いていて、日々商品と向き合いながら、販売業務に携わっています。やがては自分のアイデアや経験を活かせるような商品開発にも関わっていきたいと考えています。ちょうど、美作大学の食物学科でも商品開発を学ぶカリキュラムを作る流れがあり、将来的に、大学と何か一緒に取り組めることがあるかもしれません。
―牧原さん自身の未来の展望はありますか?
牧原:やってみたいことはたくさんあります。その中の一つとして、大学在学中に家庭科の教員免許を取得したので、教育現場にも興味があります。美作大学の先生方は本当に楽しそうに働かれていて、学生との距離も近く、みなさんとても若々しいんです。以前、70歳で退職された先生が「私はずっと学生と一緒だったから、これまで元気で楽しくやってこられた」とおっしゃっていたのが印象的でした。
将来、自分もそんな環境で学生と一緒に考えたり学んだりしながら、成長し続けられるような働き方ができたら嬉しいなと思っています。
おわりに
授業の一環でたまたま結成した2人のチームがサークルとなり、異例のスピードでクラブへと昇格。助成金がなくても活動を続けられる仕組みを整え、後輩に託して颯爽と(?)卒業。 大学2年生で立ち上げ、在学中にやり切るという、まさに“とんとん拍子”で“順風満帆”な展開は、助成金の理想的な使い方の一つと言えるのかもしれません。
「大変さを意識できないくらい楽しかった」「たくさんの個性豊かな人たちと一緒にやれることが面白かった」「依頼された話をほぼ全部受けていたら、自然とつながりが広がった」そんな言葉の端々から感じられたのは、曇りのない素直さと、迷いのない行動力。お話を伺いながら爽快感さえ覚えました。
活動のベースにあるのは、いつも「楽しい」「やってみたい」という純粋な気持ち。それがどれだけ大きな推進力になるのかを、改めて教えていただいた気がします。

成果報告書も合わせてお読みください。
美作大学調理師会
https://www.fukutake.or.jp/archive/houkoku/2023_032.html
シノノメキッチン
https://www.fukutake.or.jp/archive/houkoku/2020_077.html
美作大学調理師会
岡山県津山市北園町50
問合せ先:
TEL 0868-22-7718
FAX 0868-23-6936
mimasaka.mimacho@gmail.com
https://mimasaka.jp/

