#002 江原久美子さん
福武コレクション研究員

スミソニアン美術館が、なぜ国吉康雄の大回顧展を開催するのか
2015年4月3日からアメリカ・ワシントンD.C.のスミソニアン・アメリカン・アートミュージアム(以下、スミソニアン美術館)で開催されている国吉康雄の回顧展「The Artistic Journey of Yasuo Kuniyoshi」。同展に最も多く作品を貸し出した福武コレクションの研究員である江原久美子さん。今回の展覧会は彼女の瞳にどう映ったのだろうか。(聞き手:財団/和田広子、2015年5月19日取材)
―― こちらは何ですか。
江原 これは、スミソニアン美術館で今行われている国吉展で売られているグッズです。福武コレクションの「鯉のぼり」という作品を使ったグッズが、何種類も作られて販売されています。

―― 展覧会は4月3日からいつまで。
江原 8月30日までです。約5ヵ月間、開催されます。
―― 私のスミソニアンのイメージは、『ナイトミュージアム2』(2009年公開のアメリカ映画)。スミソニアン美術館は国立ですよね?
江原 スミソニアン美術館は、19世紀に建てられた建物を、アメリカ政府がいろいろな用途に代々使い、現在は美術館になっています。とても大きな石造りの、ギリシャ神殿のような古典的なスタイルの建物です。(注1)

―― アメリカの美術館の中で象徴的な美術館なんですか。
江原 アメリカのほとんどの美術館は、民間が運営しています。メトロポリタン美術館にしても、ニューヨーク近代美術館(MoMA)にしても民間で、個人の人たちが寄付をして成り立っている美術館です。その中でワシントンには国立の美術館としてナショナル・ギャラリーとスミソニアンの美術館がいくつかあります。スミソニアンは、美術ではなく科学や自然史の博物館というイメージが強いですよね。有名なのは、『ナイトミュージアム2』に出てきたような、恐竜がいたりとか。
―― 大きなリンカーンがいたりとか。
江原 そうそう。月の石や飛行機が展示されている科学系の博物館というイメージが強いかもしれないですが、ファインアートの美術館もあるんです。ここは、自分たちがアメリカのアートを作っていくんだという気構えがすごく強い美術館だと思います。
―― アメリカのアートを作っていく……、「ファインアート」ってなんですか。
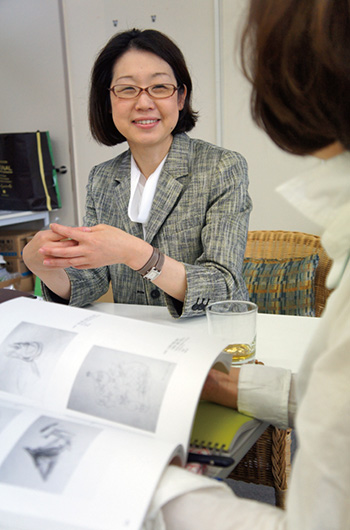
江原 今言ったのは、絵画とか彫刻のような、多くの人がいわゆる美術と思っているもの、という意味です。スミソニアンには、そういういわゆる美術ではない、科学の分野のものをたくさん収集して展示している一方で、人間がつくりうるものとして美術作品も多く扱っていて、アメリカの美術とはどういうものかを考え、発信しているんです。
―― スミソニアン美術館が、今回、国吉康雄の大回顧展をしようと思ったのはなぜですか。
江原 アメリカでは、国吉康雄を知っているのはアートの専門家だけで、一般の人にとっては、「国吉って誰?」という感じになっていたんですね。日本では国吉の展覧会が時々行われていた(注2)のに、アメリカではここ何年も大きな国吉展はなかった。アメリカのアートとしてすごく重要なのに、国吉は放っておかれているんじゃないかという意識がスミソニアンの中で生まれて、再評価しようということになったんです。アメリカンアートとして重要なんだということを、ちゃんと位置付けて知らしめようということなんですね。
―― 国吉は日本人ですけど、アメリカンアートとして重要というのはどうしてでしょう。
江原 もちろん作品が優れているというのが第一だと思います。国吉は、アメリカの美術の流れの中で、ほかの誰にも似ていないオリジナルの絵画を描いていました。それから、国吉がどういう時代に生きていたのか、それはアメリカにとってどういう時代だったのか、どういうアーティストと付き合っていたのか、美術家協会を立ち上げてその初代会長になったりしているけれど、どういう時代に誰とやっていたのか。日本というルーツがどう影響しているのか。こういうことを調べれば調べるほど、アメリカがどういう時代だったのか、誰がどう動いていたのか、ほかの国の文化をどう受け入れていたかということがすごく分かるんですよ。国吉の作品と生き方を忘れたままにするのは、アメリカの文化にとってもったいないという意識があったんじゃないかと思います。
―― それはほかのアーティストではなくて、国吉だった。
江原 国吉は重要ですが、ほかのアーティストもそうです。スミソニアン美術館は自分たちがアメリカのアートを作っていくんだ、定義していくんだと認識していて、忘れられそうになっているアーティストを掘り起こして、これもアメリカのアートとして重要ですよ、と紹介する活動をずっと続けているんです。(注3)
アメリカからのオファーに
3年前から準備を重ね
―― 江原さんはその美術展の準備段階から携わられていたわけですが、具体的に言うと。
江原 この展覧会は、福武コレクションが協力するかしないかですごく大きく変わるものだったので、準備のごく初期の段階でトム・ウルフさんが来日したときに福武總一郎さんに会って、「3年後にこういう展覧会を計画しているんだけど、協力してもらえますか」と打診されました。トム・ウルフさん(バード大学教授)は今回の展覧会の企画者の一人で、国吉を長い間研究してきた第一人者です。
―― オファーが来た。

江原 3年前からいろいろ作品を選んでこられて、2年くらい前に「これらを借りたい」という依頼が来たんです。その貸出同意書や画像を準備したり、作品そのものを貸し出せる状態にするという仕事がありました。作品は破れたり傷ついたりしているわけではないので、日本で展示するには問題ないんですが、やっぱりアメリカまで運んで長い間展示するので、それに耐えうるか、物質的に傷んでないかをチェックしたいと思って、貸し出す作品15点を、絵画の修復家に見てもらいました。「この作品のここのところがちょっと弱くなっているから、補強したほうがいい」というようなことをチェックしたんですね。その結果、必要な処置をするとこれくらいのお金がいりますという見積もりを出してもらって、福武總一郎さんに「こうしたい」と言ったら、「ぜひやろう」という返事がもらえて、作品を修復家に預けて補強や修復をしてもらうということを去年はやっていました。今、作品はとても良い状態でスミソニアンで展示されています。
―― セレクトはどなたが。
江原:今回はキュレーターが2人いるんですけれど、スミソニアンのジョアン・モーザーさんというキュレーターと、トム・ウルフさんです。

―― これがいいと。
江原 全部で66点なんですけれども、66点で展覧会をどう構成するかというのを考えて、その中で、ここにこの福武コレクションの作品が必要というのを当てはめているわけですね。
―― なるほど。実際に見られていかがでしたか。
江原 私は福武コレクションの作品は度々見ているし、岡山県立美術館の作品も見ていますけれど、今回アメリカの作品がたくさん来ていて、本物を見るのは初めて、あるいはすごく久しぶりというのが多かったんですね。私の第一印象では、やっぱり本で見るよりも色がすごくきれいだなと思いました。
―― これは、今回の図録の表紙ですよね。

江原 これはメトロポリタンが持っている作品なんですけれども、やっぱり書籍で見るのと本物を見るのでは、色が全然違いますよね。
―― この図録では暗い感じですよね。
江原 本物に比べたらちょっと沈んでいる感じで。
―― でも実際は色が明るい。
江原 鮮やかですね。晩年の色は、赤とか青とか鮮やかな色がもともと使われているのに対して、その前の時代は、茶色とか緑とかちょっと暗い感じの色が使われているんですけれども、それも本物を見ると、すごくきれいな茶色であり、すごくきれいな緑なんですよね。やっぱり国吉は色が素晴らしいなと思いました。
それからやっぱり熱というか、力が一つ一つの作品から発散されていると思いました。なぜそんな感じがしたかというと……国吉の絵って、描かれた内容は普通ありえないような幻想的なものなのに、真実味があると思うんです。国吉にとってリアルなことだったんだろうな、と思うと同時に、自分としても空々しいものではなくリアルなものとして共感できる。それが、国吉の作品に熱とか力を感じる理由かもしれないですね。

別々の美術館から貸し出されたものが一堂に出ているので、普段は一緒に並ばない作品が隣同士になっているわけですね。例えば、この作品とこっちの作品が同じテーマだったんだなということがあらためて分かって面白かったり。あと、これは日本から出ていた作品なんですけれども、筑波大学が出されている作品に描かれている女性の顔が、中国銀行さんが持っている作品と同じだというのが本物を見て分かったり。一個ずつ並べてみて、さっきこっちで見たのはこっちと関係しているんじゃないかなとか、初期で描かれていたものが、晩年にもこういうかたちであらためて描かれているんだなということが分かるというような、いろんな刺激があったと思います。あと、私も図録でしか見たことがなかった最晩年のドローイングの本物が出ていて。
―― 見たことないですね。
江原 ですよね。岡山にいると、晩年は『ミスター・エース』を描いて、次の年亡くなったという意識が強かったんですが、そのころこういうものも描いていたんです。レゾネ(作品目録)を見て知ってはいたんですが、あらためて本物を見ると、この人の心の中は一体何だったのかと……。亡くなる直前に、暗いとか重いとかだけでは言い表せないような絶望的な感じであり、かつパワフルな感じがある。そういう本物がたくさん見られたというのも、あらためて収穫でした。
国吉がどうオリジナルだったのか
その独自性を証明できれば…
―― その江原さんが見てきたものを、今度は岡山でアウトプットしていかれると思うんですけれども。
江原 今回、国吉が本当にオリジナルな、独自の創作を続けていたのだということを改めて感じ、国吉は天才だと思いましたね。福武コレクションを研究する立場として、国吉の作品をじっくり研究して発表していきたいと思っています。これまで、国吉の人生についての研究は多いのですが、作品そのものにとりくんだものは意外と少ないと思います。何が描かれているのか、どう描かれているのか、どういう素材を使ってどのような方法で描いているか。ここでは修復家の力も借りることになると思います。作品をじっくり見るなんて一見基礎的なことですが、国吉がどんなふうにオリジナルだったのか、独自性があったのかということが自分でも証明できればと思っています。
皆さんには、本物の作品を見てほしいですよね。去年、岡山シティミュージアムで展覧会をやったときに、やっぱり本物を見てもらうことで始まるものがあるなと思ったので、あまり口で言ったりするのではなくて、本物を見てほしいですね。

社内異動希望を出して直島に
現代アートを担当
―― 国吉との出会いは。
江原 大学を卒業して当時の福武書店に就職したんです。当時、1990年代の初めごろですが、企業は、お金儲けばかりするのではなく、社会の中で文化的な活動もしなくてはならない、文化に対するパトロン的な役割を果たさなくてはならないという機運が高まっていました。自分もそういうことをやってみたいなと思って、うまいことバブルの時代に入社したんですけど、当然、新人がそういう部署にすぐに配属されるわけではなくて、教材を作る部署に行ったりして5年間東京にいて、社内異動希望を出して直島に異動になったんです。
―― 直島ですか。
江原 今でいう「ベネッセアートサイト直島」を経営する部署です。当時のベネッセコーポレーションは、直島では現代アートをやって、岡山では国吉康雄美術館を運営していて、私がいた部署がその両方を担当していました。そういう状態が1990年ごろから十何年か続いていたんです。
私は主に直島の現代アートの担当だったんですが、時々国吉のほうにかかわるという感じだったんですね。岡山県立美術館に寄託するということになったときには、その事務を私が全部やりまして、リストを作って県美の人とやり取りをして、運ぶ段取りをしてお預けするというのをしましたね。

―― そのときは、国吉に対してどんな印象を持ちましたか。
江原 直島では、今、目の前にいるアーティストが、作品を作っていくんです。時間はかかりますが、直島で作品が生まれていく。まずアーティストに会って「直島はこういう場所です」というのを見てもらって、どういう作品を作るのがよいかという話をして、プランが決まってくる。大体は絵ではなくて、大がかりな仕掛けみたいな作品が多いんです。鉄を買ってくるとか、アート作品を作るために建設会社の人に工事を頼むとかいうようなことが多いんですけれど、そんなふうにして作っていくという現場をずっと見ていたので、国吉は第一に本人がもう亡くなっている、絵であるということで、ちょっと距離感がありましたね。もちろん素晴らしい世界だとは思っていましたけれど、かたちも時代もすごく違うものというような印象はありました。
―― 現代アートとは接し方が違った。
江原 直島の現代アートの美術館で仕事をしていたときに、ギャラリーツアーとかしますよね。そのときに、現代アートだからわかりにくい、という印象が強いんです。でも何とかして知りたいと思って来る人たちに対してすごくやってしまいがちなのが、「つくった本人はこう言っていました」と言うことなんです。特に新聞記者の方によく聞かれるのは、「この作品は、何を伝えようとしてるんですか」って。
―― コンセプトは何ですかと。
江原 と言われて、「こうですよ」と言えるものじゃないわけですよ。逆に絶対言ってはいけないと思っていました。アーティスト本人と話をしているときに、面白いことを言うなという瞬間はあるんですけれども、本人はやっぱり「作品を見てほしい。自分の言いたいことはここに込めてあるから」と必ず言うわけで、それで何とかできないかなと、現代アートの美術館の担当だったときにはずっと思っていたんですね。
つまり、作品はここにありますと。それを見る人は目の前で見ているにもかかわらず、「本人はこう言っていましたよ。こういうことを分かってほしいと言っていましたよ」と言ってしまうと、見ている人と作品の関係がなくなるというか、聞いただけで分かってしまうという感じになるので、「いや、よく見ましょうよ」というふうにしようとしていたんですね。「本人がどういう人かというのは、もういいじゃないですか。だれが描いたかとか、だれが作ったかとか、男か女かとか、年寄りか若いかとか、別にいいじゃないですか。とにかくこの作品を見ましょう」というふうに、私はずっとやっていたんです。
国吉にかかわるようになって
アーティスト本人について語るようになった
―― 今は「国吉ってこういう人だ」とすごく語っていますよね。

江原 そうなんです。すごく語っているんですよ。だから、私はそれがすごい悩みだったんですね。国吉にかかわるようになって、それまでのやり方だと、「本人のことはいいじゃないですか。絵を見てこの不思議さをみんなで語ろう」ということを是非したかったんですけれど、国吉の場合、本人のことを分かったほうがより面白いというふうに切り替えたんですね。無理というか、もったいない。本人のことを全然知らずに絵だけ見て楽しもうというよりも、この人はこういう人で、こういうことを言っていたんですよということがちょっとでも分かったほうが、より作品が面白くなるタイプのアーティストだなと思って、切り替えたことがありますね。
対話型鑑賞でいうと特にそうなんですけれども、対話型鑑賞って、作品と見る人の関係だけが一番大事で、時々ちょっとヒントを言ってもいいけれども、この人はこういう人でこういうことを言ってましたというのを、言わないことにしてるじゃないですか。森弥生さんと話をしていても、「そこがいつも悩みです」と言われていたんですけど、国吉についてはやっぱり時代と人を言ったほうがいいなと、すごく語ることになってしまいました。
―― 国吉も当時は現代アートだったと思うんですけど、当時生きている方はその背景も知っているし、その時代に生きているから、その絵だけを見て感じたらよかったのかもしれないですよね。
江原 そうですね。今私が現代アートの作品について「本人はいいから絵を見ましょう」と言っているのと同じように、当時の人も、「絵そのものが面白いよね」と言っていたかもしれないですね。
―― 背景も全然違うしね。
江原 当時、日本人がアメリカで生活して画家として暮らしていたということに、今の私たちにとっての意味ができているのかもしれないですよね。この人がアメリカ生まれのアメリカ人で、アートの文脈に沿った画家だったら、別にそんなことをあまり気にしなくてもよかったかもしれないですけれど、人生もセットで見たほうが、より意味があると思いますね。それは現代アートをやっていたときと違うところです。

―― 距離は縮まりましたか。
江原 そうですね。でも本人と会えないというか、作品とか文字を読んでしか出会えない。たまに、録音を聞いたりするチャンスもあったりするんですけど。
もし国吉本人にいま会えたら
どんな価値観を持っているのか知りたい
―― 今、本人に会ったら何が聞きたいですか。
江原 聞き方は難しいですけど、どういう価値観を持った人なのかなということを知りたいと思いますね。何を面白がっているのか、何に興味を持っているのかというのを聞いてみたいなと思います。 すごく基本的な質問ですけど……。国吉には、絵を描いている以外の姿があったんじゃないかと思います。生活の中ではどういう人だったのかなということに興味があります。
現代アートのアーティストって、ものすごくいろんな人がいるんですよね。絵を描いてなかったら犯罪者だったんじゃないかというような人もいますし、手を動かしてないとこの人は生きていけないのかなという人もいますし、割とエスタブリッシュされて、美術業界で生きていくには次はこうやったらいいと、戦略的に動ける人もいたり。もちろんそれだけではだめで、才能は絶対に必要なんですけれど。本当にいろんな人がいるんですよね。みんな当然、アートに命をかけていますけれど、ある一定の「絵描きさん」みたいなイメージがあるわけじゃなくて、本当に、普段、会社員生活をやっているよりももっといろんな人がいるというのがアートの世界なんです。そういう中において、もし今国吉が生きていたらどんな人だったのかなというのは思います。でもきっと、何かすごく理想を持っていた人なんだろうなとは思いますね。
―― アート・スチューデンツ・リーグにも理想を持って入った。
江原 まず学生として入ったときに、それまでいくつも美術学校を転々として、ほかの学校は、やっぱり合わないと思っていた中で、リーグは肌にあったみたいで、何年間が過ごして、友達もできたし奥さんも見つけています。リーグをやめて、画家になったあとにまた先生になって、亡くなる直前まで先生を続けていたので、一つの大きな生きがいというか、欠かせないものだったと思います。
―― 教えるということが。

江原 アートを志す人たちに教えるということが、国吉にとっても必要だったと思います。でも、平和な時代の揺るぎない地位の人ではなかったので、やっぱり言ってみればフリーの画家であるよりも、学校の先生であるという地位が必要だったのだろうなとも思います。そういうふうに、本人の意思だけでは生きていけなかったし、こうせざるを得ないとか、こうすることが何かの手段になるというようなことが、すごく複雑に絡んでいると思います。
―― 一つひとつ紐解いていくんですね。
江原 そうなんですよ。何十年前のアメリカというものをまず知らないといけないですよね。それがまず膨大な大きな世界であるわけですし、そこで日本人が暮らしたというのがどういうことなのかというところからして。この間アメリカに行って、なるほどと思ったところもあったんですけれど、やっぱりそういう経験をすごく積んでいかないと、簡単には言えないというところはあるんです。だから今は、結構自分に義務を課して一生懸命岩盤を削っていくというような感じで、「わあ、面白い」というよりも、頑張らないといけないという感じはあります。
でも何が動機かといいますと、やっぱり勇気をもらえるというか。自分が今生きているのは平和な時代で、岡山県で生まれて岡山県で暮らしているから、別にそんなに危険はないわけですけれど。
―― 危機感はないですよね。
「国吉さんもあんなに頑張ったんだし、
私も頑張らなきゃ」と
江原 ないですよね。普通に暮らしていれば、このまま年をとっていけるはずですけれども、でもやっぱり、どうやって生きていったらいいのかな、子どもをどう育てたらいいかな、これからの時代はどうなっていくのかなとか思うときに、「いや、でも国吉もあんなに頑張っていたし」と思って。決して流されていたわけじゃなくて、自分で切り開いていったわけですね。やらなければやらなくて済んだことを、あえて自分でどんどんやっていった人なので、やっぱり自分も頑張ろうという勇気というか元気というか、頑張らなきゃなと思うんですね。国吉に関わらなかったら、そういうふうに思わなかったと思います。それは実感しますね。
福武總一郎名誉顧問も、経営をやっていく上で国吉にすごく触発されたというようなことを言っているわけですけれども、その気持ちはせんえつながら分かるなと。絵描きで研究の対象というよりも、もっと「国吉さんもあんなに頑張ったんだし、私も頑張らなきゃ」と思うというつながりは感じますね。ほかの方はどうか分からないですけれども、それは、人物を研究する研究者の人はそうなのかもしれないですね。学問の対象という知的好奇心だけではないところが、私の場合はあるなとは思いました。
―― 人として興味が。
江原 本当に会ったら、付き合いやすい人だったのか、付き合えていたのか分からないなと思って、ちょっと怖い気はしますね。もしかしたら、取っつきにくい人だったのかもしれないなとか。資料を読むと、学生に慕われていたとか、社会活動に関わっていたときもすごく人格的に信頼されていて、誠実で付き合いやすい人だったと友達たちが言っていたりするんです。だからきっと会ったら、「ああ、いい人だな」と思えるかもしれないんですけど……。でも、こういう絵を描く人だよ、とは思うんですよ。「なんだこりゃ」という絵を。もし付き合いやすい人だったとしたら、すごく内面を隠していたんじゃないかなとか、それが時々出てくるようなことがあったら、奥さんはすごく大変だったんじゃないかと思って。
―― 私から言わせたら、すべて「なんだこりゃ」みたいな作品なんですけど。
江原 本当にそうなんですよね。すべて「なんだこりゃ」なんですよね。本当にパワーがすごいんですよね。だから美術史的に、画家としてこういうものを描きたいと思って、他の人にこういう影響を与えましたというだけじゃないんですよね。もっと「人間って何」ということを考えさせられる。
江原 もう一つ私が興味があるのは、当時のアメリカ人が何で国吉を評価したのかを知りたいと思って。そのあと何十年かは忘れられるというか、アメリカの美術史ではほかの流れができてしまうんですけれど。でも国吉が生きていた1920年代から40年代くらいというのは、アメリカ人が国吉を認めていて、美術館が買ったり個人が買ったり、ヴェネツィア・ビエンナーレの代表に出したりしているわけなので、何を面白いと思ったのかなというのはぜひ知りたいと思っていますね。
よく言われるのが、アメリカは若い国なので、オリジナルのアートを一生懸命作ろうとしていた。それまでずっとヨーロッパのまねをしていたんだけれども、国の力が付いてきて、オリジナルのアートを作ろう、アメリカンアートって何だということがすごく言われていて、国吉はヨーロッパではない、本当にオリジナルだよねという評価はあったみたいなんです。けれど、そういう意識を持っていない人が見ても面白いと思ったとすると、例えば一般のコレクターの人が、「私これ好き」って思ったとしたら、何でかなと思うんですよね。さっきからずっと言っているように、「なんだこりゃ」というような、ここに何かすごい世界があるということかもしれないし。
―― 自宅には飾りたくないです。(笑)

江原 でも結構飾っていたみたいですよ。飾りやすいように、果物の絵とかリトグラフを描いていたらしいですけど。私が思うのは、何か物語性というか。例えば、皆さん小説を読むじゃないですか。明らかに虚構の世界というかフィクションの世界で、それを学んだからといって知識が高まるとかじゃなくて、面白いから読んでいるわけですね。この人一体どうなっちゃうのかなとか、こういうときにこの人とこれからどうなっちゃうのとか、物語を読むことを、人々の心が必要としているのだとすると、国吉の作品ってそんな感じだったんじゃないかなと。
当時のアメリカの人にとって、お話、物語というものが必要だったんじゃないかなと思っています。村上春樹とか河合隼雄さんが、物語の力というふうによく言っていて、村上春樹の小説って、結構とっぴというか現実にはあり得ない設定じゃないですか。だけど、すごくたくさんの人がそれを必要としているわけですよね。国吉の時代に国吉の作品を見て、アメリカ人たちがそれと同じようなことを必要としたんだろうなというふうに、私は妄想としては思います。こうだったんじゃないかなと想像して、ああやっぱりというような、イマジネーションがかなり必要ですね。
―― 妄想が。
江原 妄想が必要です。本当に
―― 江原さんは今、妄想中。
江原 うん、頑張っています。
- 注1: スミソニアン博物館群:ワシントンD.C.を拠点とする科学、産業、技術、芸術、自然史の博物館と教育機関の複合体。スミソニアン学術協会が運営し、アメリカ合州国連邦政府が主な財源を担っている。19の博物館と教育機関のうち多くがワシントン.D.C.にある。
- 注2: アメリカでは1986年にホイットニー美術館で国吉康雄展が開かれたあと、大きな美術館での国吉展は開かれなかった。一方日本では、1989年京都国立近代美術館ほかでの生誕100周年記念展、2004年東京国立近代美術館ほかでの巡回展、2006年岡山県立美術館、2012年横須賀美術館での企画展など数年ごとに国吉康雄の展覧会が開かれている。
- 注3: スミソニアン・アメリカン・アートミュージアムの使命は、「アメリカ美術を収集し、理解し、楽しむことに専念する。彼らの作品がアメリカの経験と世界的とのつながりを反映するアーティストの並外れた創造力を、この美術館は賞賛する。」国吉康雄を再評価しようという意志は、ここから生まれている。

